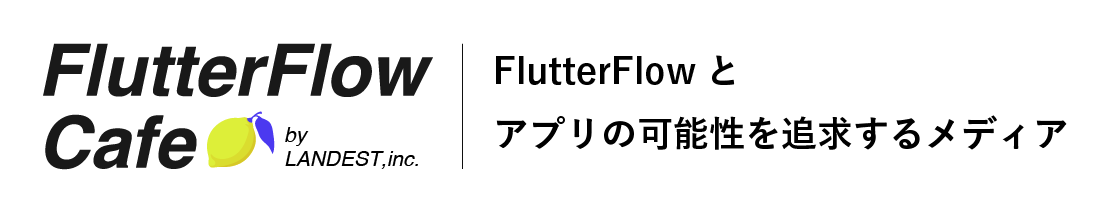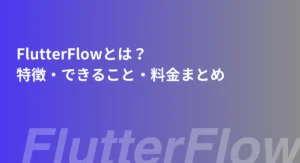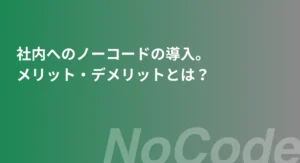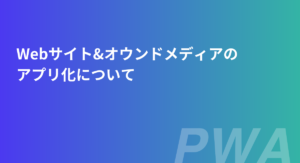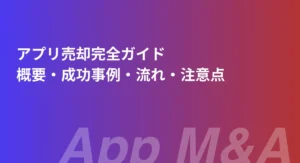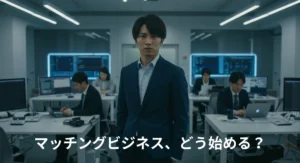ノーコード研修を導入すべき企業の特徴とは?失敗しない見極めポイント
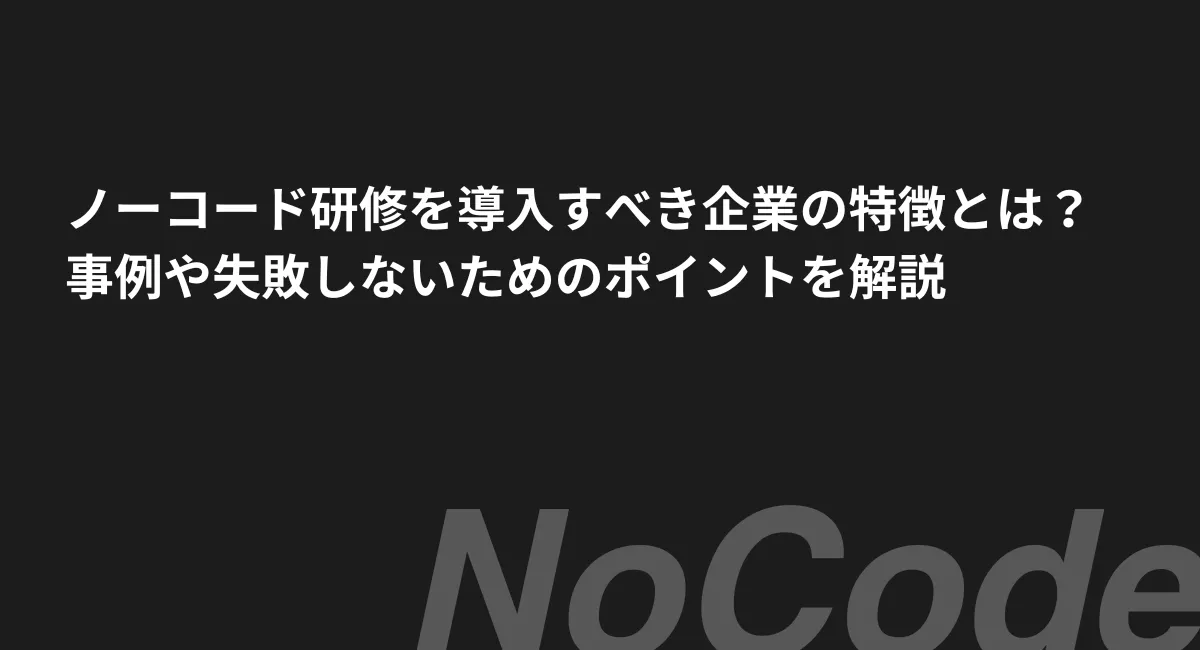
昨今、IT人材不足が深刻化する中、プログラミング知識がなくてもアプリ開発ができる「ノーコード」技術が注目を集めています。そして多くの企業がノーコード研修の導入を検討するようになりました。
しかし、「本当に自社にノーコード研修は必要なのか?」「どんな企業が導入すべきなのか?」と悩む担当者も少なくありません。
本記事では、ノーコード研修を導入すべき企業の特徴や、導入前に確認すべきポイント、失敗しないための具体的な対策を解説します。ぜひ、自社への導入判断の参考にしてください。
ノーコード研修とは
ノーコード研修とは、プログラミングコードを書かずにアプリケーションやシステムを開発できる「ノーコードツール」の使い方を学ぶための教育プログラムです。従来のプログラミング研修と異なり、専門的なコーディング知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作でアプリ開発のスキルを習得できます。
ノーコード研修の主な内容は以下のようなものです:
- ノーコードツールの基本操作方法
- ビジネスアプリケーション開発の基礎知識
- データベース設計の基本概念
- ワークフローやプロセス設計
- 実践的なアプリ開発演習
- 開発したアプリの運用・保守方法
特に企業向けのノーコード研修では、業務効率化や社内DX推進を目的としたアプリケーション開発に重点を置いたカリキュラムが多く、実務での活用を想定した実践的な内容が特徴です。
「アプリのアイディアはあるけど、実現する方法が分からない!」という方へ。
数々のアプリをFlutterFlowで開発してきた”FlutterFlow Cafe”運営会社が無料で相談に乗ります。
ーご相談はこちらから
・マッチングアプリ
・ライブEコマースアプリ
・生成AIを使ったサービス
などなど、アイディアをまずはお聞かせください。
▶︎こちらのリンクから質問に答えるだけでアプリ企画書が出来上がる資料もプレゼントしております。
ノーコード研修を導入すべき企業の7つの特徴
すべての企業にノーコード研修が必要というわけではありません。以下の特徴に当てはまる企業は、ノーコード研修の導入を検討する価値があるでしょう。
1. IT人材の採用・確保が難しい企業
IT人材の獲得競争が激化する中、専門的なプログラマーやエンジニアの採用に苦戦している企業は多いでしょう。ノーコード研修を導入することで、既存の社員がITスキルを獲得し、社内のIT人材不足を補うことができます。
専門的なプログラミング知識を持つエンジニアを採用する代わりに、現場の業務知識を持つ社員がノーコードでアプリ開発できるようになれば、人材確保の課題を解決できます。
2. 業務システムの内製化を進めたい企業
システム開発を外部ベンダーに依存している企業では、仕様変更の度に時間とコストがかかる課題があります。ノーコード研修によって社内での開発能力を高めることで、簡易的な業務システムの内製化が可能になります。現場のニーズに合わせて迅速にシステム改修ができるようになれば、業務効率化やコスト削減につながります。
3. DX推進を強化したい企業
デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進したいものの、リソース不足で思うように進まない企業も多いでしょう。ノーコード研修を実施することで、各部門でDXを担う人材を育成でき、全社的なDX推進を加速させることができます。現場主導でデジタル化を進められるため、トップダウンだけではなくボトムアップのDX推進が可能になります。
4. 業務改善のボトルネックがIT部門にある企業
多くの企業では、業務改善のためのシステム開発・改修がIT部門に集中し、ボトルネックとなっています。ノーコード研修によって各部門でアプリ開発ができる人材を育成することで、IT部門への依存度を下げ、業務改善のスピードを向上させることができます。現場が自ら必要なツールを開発できれば、IT部門の負荷も軽減されます。
5. 部門間の連携強化が必要な企業
部門ごとに異なるシステムやツールを利用しているため、情報共有や連携がスムーズでない企業もあるでしょう。ノーコード研修を全社的に実施することで、共通のプラットフォームでアプリ開発・運用する文化を醸成でき、部門間連携の強化につながります。統一されたアプローチで業務アプリを開発することで、サイロ化した組織の壁を越えた情報共有が促進されます。
6. プロトタイピングの高速化を図りたい企業
新サービスや新製品の開発において、アイデアを素早くプロトタイプ化したい企業にもノーコード研修は有効です。ノーコードツールを使えば、企画段階からすぐにアプリのプロトタイプを作成でき、検証サイクルを高速化できます。「作って試す」文化を定着させることで、イノベーション創出のスピードも向上します。
7. シャドーITのリスクが高まっている企業
現場が勝手にクラウドサービスを導入している「シャドーIT」の問題を抱える企業も少なくありません。ノーコード研修を提供し、公認された安全なプラットフォームでの開発を促すことで、シャドーITのリスクを軽減できます。管理されたノーコード環境で業務アプリを開発することで、セキュリティとガバナンスを確保しながら現場のニーズに応えることが可能になります。
ノーコード研修導入の5つのメリット
ノーコード研修を導入することで、企業には以下のようなメリットがあります。
1. 非エンジニアでもアプリ開発スキルが身につく
ノーコード研修の最大のメリットは、プログラミング経験がない社員でもアプリ開発のスキルを習得できることです。マーケティング、営業、人事など、様々な部門の社員がビジネスニーズに合わせたアプリケーションを自ら開発できるようになります。これにより、IT人材に依存せず、現場主導でのデジタル化が可能になります。
2. 開発コストと時間の大幅削減
外部ベンダーに依頼する場合と比較して、社内でノーコード開発ができれば、開発コストを大幅に削減できます。また、仕様変更の度に発注・開発のサイクルを繰り返す必要がなくなるため、開発期間も短縮されます。小規模な業務改善なら数時間〜数日で完了するケースも多く、ビジネススピードの向上につながります。
3. 現場のニーズにピンポイントで対応可能
現場の業務を熟知した社員自身がアプリを開発するため、実際のニーズに即したシステムを構築できます。外部ベンダーに依頼する際の要件定義の難しさや認識のズレを解消し、本当に必要な機能を備えたアプリケーションを効率的に開発することが可能です。また、利用しながら迅速に改善できる点も大きなメリットです。
4. DX人材の社内育成につながる
ノーコード研修は単なるツールの使い方だけでなく、業務プロセスの設計やデータ活用の考え方なども学ぶことができます。これにより、デジタル思考を持ったDX人材を社内で育成することができ、全社的なデジタル変革の推進力となります。技術的なスキルと業務知識を兼ね備えた「ビジネステクノロジスト」の育成にもつながります。
5. 部門を越えた協業文化の醸成
ノーコード研修を全社的に実施することで、共通言語や共通のアプローチが生まれ、部門を越えた協業が促進されます。例えば、営業部門と顧客サポート部門が連携してカスタマージャーニーを可視化するアプリを共同開発するなど、横断的な業務改善プロジェクトが生まれやすくなります。組織の風通しが良くなり、イノベーションが起きやすい環境が整います。
ノーコード研修導入の3つの注意点
一方で、ノーコード研修を導入する際には以下の点に注意が必要です。
1. ノーコードでもすべてが解決するわけではない
ノーコードツールは進化していますが、複雑な処理や高度なカスタマイズには限界があります。特に以下のようなケースでは、専門的なプログラミングが必要になる場合があります:
- 大量データの高速処理が必要なシステム
- 複雑なアルゴリズムを実装する必要がある場合
- 特殊なハードウェアとの連携
- 極めて高いセキュリティが求められる機密システム
ノーコード研修を導入する際は、そのツールでできることとできないことを正しく理解し、適用範囲を見極めることが重要です。場合によっては、ノーコードとプロフェッショナル開発の使い分けも検討しましょう。
2. ガバナンス体制の整備が必要
ノーコード開発を推進すると、社内に多数のアプリケーションが乱立するリスクがあります。これを防ぐためには、以下のようなガバナンス体制の整備が必要です:
- アプリ開発の申請・承認フロー
- セキュリティガイドラインの策定
- データアクセス権限の管理
- 重複開発を防ぐためのアプリ管理台帳
- 品質基準とレビュープロセス
ノーコード研修と並行して、こうしたガバナンス体制の構築も検討する必要があります。
3. 既存IT部門との関係性に配慮
ノーコード開発を推進すると、既存のIT部門との役割分担や関係性に影響が出る可能性があります。IT部門が「業務が奪われる」と感じると、抵抗が生まれることもあるでしょう。
これを防ぐために、以下のような配慮が必要です:
- IT部門を巻き込んだ研修計画の策定
- ノーコード開発とプロフェッショナル開発の棲み分けの明確化
- IT部門のノーコード開発支援者(エバンジェリスト)の育成
- ノーコード開発者とIT部門の連携モデルの構築
IT部門とビジネス部門の協業を促進する形でノーコード研修を位置づけることが重要です。
失敗しないノーコード研修導入の6つのポイント
ノーコード研修を効果的に導入するためには、以下のポイントを押さえましょう。
1. 明確な目的と期待値の設定
ノーコード研修を導入する目的を明確にしましょう。「IT人材不足の解消」「業務効率化の促進」「DX推進」など、具体的にどのような成果を期待するのかを定義します。また、研修後にどのようなアプリケーションを開発できるようになることを期待するのかも明確にしておきましょう。
例えば、「3ヶ月以内に各部門で1つ以上の業務改善アプリを開発する」といった具体的な目標を設定することで、研修の効果測定もしやすくなります。
2. 適切なノーコードツールの選定
ノーコードツールは多様であり、それぞれ得意分野や特徴が異なります。自社の業務内容やニーズに合ったツールを選ぶことが重要です。以下のような観点から選定しましょう:
- 開発したいアプリケーションの種類(業務アプリ、モバイルアプリ、Webサイトなど)
- 必要な連携機能(既存システムとの連携、API連携など)
- ユーザー数や拡張性の要件
- セキュリティ要件
- 日本語サポートの有無
- コスト(ライセンス料、研修費用など)
多くの企業では複数のノーコードツールを目的に応じて使い分けることもあります。
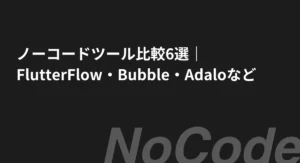
3. 研修対象者の適切な選定
ノーコード研修の効果を最大化するためには、適切な受講者を選定することが重要です。以下のような特性を持つ社員が適任と言えるでしょう:
- 業務改善に対する高いモチベーション
- 論理的思考力がある
- デジタルツールへの抵抗感が少ない
- 業務知識が豊富
- チームをリードする立場にある
初期段階では、各部門から「デジタル推進リーダー」を選出し、集中的に研修を行う方法が効果的です。その後、リーダーが部門内で知識を広げていく「トレーナー育成型」のアプローチも検討しましょう。
本メディアFlutterFlow Cafe運営の株式会社ランデストでは、豊富なノーコード開発実績を活かし、法人向けにノーコード研修をしております。
以下フォームよりお気軽にご相談くださいませ。
「アプリのアイディアはあるけど、実現する方法が分からない!」という方へ。
数々のアプリをFlutterFlowで開発してきた”FlutterFlow Cafe”運営会社が無料で相談に乗ります。
ーご相談はこちらから
・マッチングアプリ
・ライブEコマースアプリ
・生成AIを使ったサービス
などなど、アイディアをまずはお聞かせください。
▶︎こちらのリンクから質問に答えるだけでアプリ企画書が出来上がる資料もプレゼントしております。
4. 段階的な研修プログラムの設計
効果的なノーコード研修は、一度の集中講義ではなく、段階的なプログラムとして設計することが重要です。
例えば以下のような段階が考えられます:
- 基礎知識習得:ノーコードの概念やツールの基本操作を学ぶ
- 簡易アプリ開発:簡単なアプリを実際に作成してみる
- 実務適用検討:自部門の業務課題を洗い出し、ノーコードで解決できそうな課題を特定する
- 実践プロジェクト:実際の業務課題を解決するアプリを開発する
- フォローアップ:開発したアプリの改善点や発展させる方法を学ぶ
また、座学だけでなく、ハンズオンやワークショップ形式の実践的な内容を取り入れることで、習得度が高まります。
5. 実践的な課題設定とフォローアップ
ノーコード研修では、実際の業務課題を題材にした実践的な演習が効果的です。「架空の例」ではなく、「自部門の実際の課題」を解決するアプリを開発することで、学習意欲と定着度が高まります。
また、研修終了後も継続的なフォローアップの機会を設けることが重要です。例えば:
- 定期的な成果発表会
- トラブルシューティングの相談会
- 優秀事例の表彰制度
- コミュニティ形成によるナレッジ共有
こうした仕組みにより、研修で得たスキルを実務で継続的に活用することが促進されます。
6. 経営層のコミットメントと推進体制の構築
ノーコード研修の効果を最大化するには、経営層のコミットメントと全社的な推進体制が不可欠です。特に以下の点が重要です:
- 経営層からのメッセージによる重要性の発信
- 研修参加のための時間確保
- 成功事例の全社共有と評価
- 推進事務局の設置
- IT部門との連携体制の構築
トップダウンとボトムアップの両面からノーコード開発を推進する体制を整えましょう。
法人向けノーコード研修の種類と選び方
法人向けのノーコード研修には、以下のような種類があります。自社の状況に合わせて最適な研修形態を選びましょう。
1. ツールベンダー提供の公式トレーニング
ノーコードツールのベンダー企業が提供する公式トレーニングです。ツールの機能を網羅的に学べる点が強みです。
メリット:
- 最新の機能や使い方を正確に学べる
- 公式認定資格を取得できる場合がある
- ベンダーのサポートを直接受けられる
デメリット:
- 一般的な内容が中心で、自社の業務に特化した内容ではない
- 英語での提供が多く、日本語対応していない場合がある
- 受講料が高額な場合がある
2. 専門研修会社によるカスタマイズ研修
ノーコード開発の研修を専門とする会社によるカスタマイズ研修です。自社の業務に合わせた内容にカスタマイズできる点が強みです。
メリット:
- 自社の業務課題に合わせた内容にカスタマイズ可能
- 日本語での研修が可能
- 複数のツールを横断的に学べる場合もある
デメリット:
- ベンダー公式と比べて最新機能への対応が遅れる可能性
- 講師のスキルによって品質にばらつきがある
- 比較的コストが高い
3. オンライン学習プラットフォーム
Udemyなどのオンライン学習プラットフォームで提供されるノーコードコースです。低コストで自分のペースで学べる点が強みです。
メリット:
- 低コストで導入可能
- 自分のペースで学習できる
- 様々なレベルやツールのコースがある
デメリット:
- 自主学習となるため、モチベーション維持が難しい
- 質問やフィードバックを得にくい
- 体系的な学習プランが立てにくい
4. 社内講師による内製研修
ノーコード開発に詳しい社内人材を講師として育成し、内製の研修プログラムを構築する方法です。自社の文化や業務に完全にフィットした内容にできる点が強みです。
メリット:
- 自社の業務やシステム環境に完全にマッチした内容
- 長期的には低コストで運用可能
- 講師も教えることで成長できる
デメリット:
- 社内講師の育成に時間とコストがかかる
- 外部の最新動向を取り入れにくい
- 講師の負担が大きい
選び方のポイント
ノーコード研修を選ぶ際は、以下のポイントを考慮しましょう:
- 規模と予算:対象人数や予算に合わせた研修形態を選ぶ
- カスタマイズ度:汎用的な内容で良いか、自社業務に特化した内容が必要か
- 継続性:一度きりか、継続的な育成プログラムとして実施するか
- ツールの選定状況:特定ツールに決まっているか、複数ツールを比較検討中か
- 受講者のITリテラシー:受講者の現在のスキルレベルに合った内容か
多くの企業では、初期は外部の専門研修を利用し、徐々に社内講師を育成して内製化していくアプローチが効果的です。
ノーコード研修の成功事例3選
ノーコード研修を効果的に導入した企業の成功事例を紹介します。
事例1:丸和繊維工業株式会社「現場主導のDX推進を実現」
背景と課題: 丸和繊維工業株式会社は、生産管理のデジタル化を進めたいと考えていましたが、何から取り掛かれば良いか悩んでいました。
導入したノーコード研修: 東京商工会議所墨田支部が開催する、IT担当者育成のためのセミナーを受講。プログラミング不要のアプリ開発ツールを用いて知識を学び、実際に自らアプリを開発しました。
成果:
- 業務に直結するアプリケーションを開発し、社内での運用を開始。
- コストは制作者の人件費のみで、効率的なDX推進を実現。
成功の要因: セミナー講師に相談しながら、業務外のアプリから開発を始めることで、スムーズにノーコード開発に取り組むことができました。
出典:東京商会議所
事例2:アイシン高丘株式会社「非エンジニアによる業務自動化を実現」
背景と課題: 社内のシステム開発において、システム部門と利用部署とのすり合わせに時間がかかり、スピード感のある開発ができていませんでした。
導入したノーコード研修: Power Automate Desktopを活用した研修を実施。初学者を対象に、講師がテキストに掲載されていない内容も取り入れ、好奇心を学習につなげるような研修を行いました。
成果:
- 非IT人材が自らノーコードツールによる開発に取り組むようになった。
- 請求書の入力作業を自動化するなど、業務効率化を実現。
成功の要因: 初学者向けの柔軟な研修内容と、実務に直結した課題への取り組みが、非エンジニアの積極的な参加を促しました。
出典:インターネットアカデミー
事例3:オレンジトーキョー株式会社「生産管理アプリで業務効率化を実現」
背景と課題: 生産効率を上げる方法を模索していたオレンジトーキョー株式会社は、生産能力を把握するための仕組みづくりに着手しました。
導入したノーコード研修: プログラミング不要の開発ツール「Adalo」を使用し、株式会社セラピアのサポートのもと、2カ月間の研修を受けてアプリ開発に取り組みました。
成果:
- 編み機の生産管理アプリを開発し、作業効率が向上。
- 生産計画の立案がより効率的になり、業務の見える化を実現。
成功の要因: 現場のニーズに即したアプリ開発と、現場での使いやすさを意識した設計が、業務効率化に直結しました
出典:東京商会議所
まとめ:ノーコード研修導入の判断基準
本記事では、ノーコード研修を導入すべき企業の特徴から、具体的な導入ポイントまで解説してきました。最後に、自社へのノーコード研修導入を判断するための基準をまとめます。
ノーコード研修導入の判断チェックリスト
以下の項目のうち、3つ以上当てはまる場合は、ノーコード研修の導入を検討する価値があります:
□ IT人材の不足や採用難が課題となっている
□ 業務システムの開発・改修に時間とコストがかかっている
□ 現場からの業務改善要望にIT部門が対応しきれていない
□ 部門ごとに散在するExcelやアクセスでの業務管理を改善したい
□ DX推進を全社的に加速させたい
□ デジタル人材の社内育成が急務となっている
□ システム開発の内製化を進めたい
□ 業務プロセスの可視化と標準化を進めたい
□ 現場主導での業務改善文化を醸成したい
□ プロトタイピングのスピードを高めたい
ノーコード研修の導入を検討する際は、本記事の内容を参考に、自社にとって最適な形での導入を目指してみてください。弊社でもお手伝い可能ですので、お気軽にお声がけくださいませ。
「アプリのアイディアはあるけど、実現する方法が分からない!」という方へ。
数々のアプリをFlutterFlowで開発してきた”FlutterFlow Cafe”運営会社が無料で相談に乗ります。
ーご相談はこちらから
・マッチングアプリ
・ライブEコマースアプリ
・生成AIを使ったサービス
などなど、アイディアをまずはお聞かせください。
▶︎こちらのリンクから質問に答えるだけでアプリ企画書が出来上がる資料もプレゼントしております。